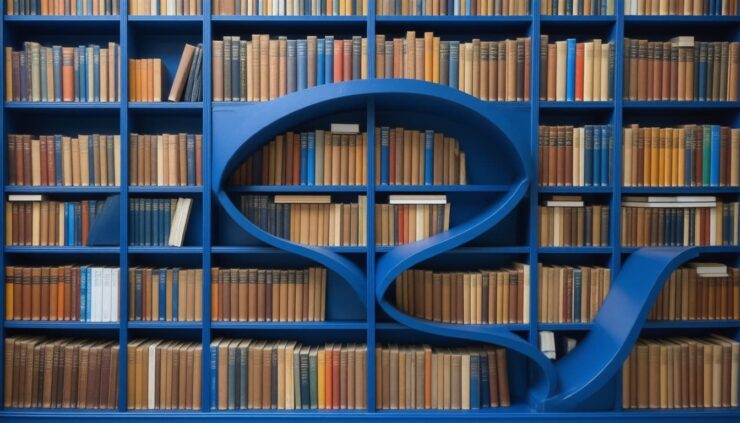最近心理学の本とか読んでます。
勉強して見つけた心理学の用語を40選。
まあメモ代わりみたいな記事です。
暗いニュースに引っ張られすぎないように、
楽しい気分をたくさん味わえますように、
モノゴトを穏便にできれば有利に進められたらなおよし。
人間関係で悩む時間を減らしたい
あなたに。
目次
1〜10
1. 確証バイアス
- 自分の考えに合う情報ばかりを集め、反する情報を無視する心理傾向。
- 例えば、自分が「A社は素晴らしい」と思っていると、A社の良いニュースばかりを探し、悪いニュースを無視してしまう。
- SNSでの情報収集や、友人との会話などで起こりやすい。
- 客観的な判断を妨げる可能性があるため、注意が必要。
2. 認知的不協和
- 矛盾する考えを持つときに感じる不快感。
- 例えば、「タバコは体に悪い」と知っていながら、「ストレス解消になるから」と吸い続けてしまう状態。
- この不快感を解消するために、考え方を変えたり、行動を正当化したりする。
- 認知的不協和を解消しようとする心理が、行動に影響を与える。
3. アンカリング効果:
- 最初に提示された情報に影響されやすい心理現象。
- 例えば、商品の値段交渉で、最初に高い金額を提示されると、その後の金額が安く感じてしまう。
- 価格交渉や、プレゼンテーションなどで利用される。
- 最初に提示する情報によって、相手の判断を誘導することができる。
4. バンドワゴン効果:
- 他の人がしていることを真似したくなる心理。
- 例えば、流行している服や音楽に興味を持ってしまう。
- SNSでの口コミや、ランキングなどで影響を受けやすい。
- 人気があるものに、さらに人気が集まる現象。
5. プラシーボ効果:
- 実際には効果がないものでも、信じることで効果が現れる現象。
- 例えば、偽薬を飲んだだけでも、症状が改善することがある。
- 医療現場や、心理療法などで利用される。
- 心の持ち方によって、身体に影響を与えることができる。
6. ハロー効果:
- 一つの良い特徴があると、他の特徴も良く見えてしまう心理。
- 例えば、外見が良い人は、性格も良いように思われてしまう。
- 人事評価や、マーケティングなどで利用される。
- 外見だけでなく、内面も磨くことが大切。
7. カリギュラ効果:
- 禁止されると逆にやりたくなる心理。
- 例えば、「見るな」と言われると、つい見てしまう。
- 広告や、イベント告知などで利用される。
- 興味を引くために、あえて禁止する表現を使うことがある。
8. ザイオンス効果:
- 同じ人に何度も会うと好感度が増す現象。
- 例えば、何度も顔を合わせるうちに、親近感が湧いてくる。
- 営業や、恋愛などで利用される。
- 繰り返し接することで、相手との関係性を深めることができる。
9. ゲイン・ロス効果:
- 相手の評価が徐々に上がると、より好感を抱く心理。
- 例えば、最初は苦手だった人が、徐々に親しくなっていくと、より好きになる。
- 恋愛や、人間関係構築で利用される。
- ギャップ萌えとも関連する。
10. ディドロ効果:
- 新しい物を手に入れると、それに合わせて周りの物も欲しくなる心理。
- 例えば、新しいスマホを買うと、それに合うケースやアクセサリーも欲しくなる。
- 消費行動を促すために、マーケティングで利用される。
- 関連商品をまとめて販売することで、購買意欲を高める。
11〜20
11. ヴェブレン効果:
- 高価な物を持つことで優越感を得ようとする心理。
- 例えば、高級ブランド品を持つことで、周りの人よりも優位に立ちたいと思う。
- ステータスシンボルとなる商品に起こりやすい。
- 見栄や虚栄心とも関連する。
12. スノッブ効果:
- 他の人と違うものを持ちたがる心理。
- 例えば、流行しているものでも、あえて違うものを選ぶ。
- 個性をアピールしたい人に起こりやすい。
- 限定品や、希少価値の高い商品に惹かれる。
13. ドア・イン・ザ・フェイス:
- 要求をエスカレートさせて、最終的に小さな要求を通すテクニック。
- 例えば、最初に大きな要求を断らせておき、次に小さな要求をすると、受け入れられやすくなる。
- 交渉や、セールスなどで利用される。
- 譲歩することで、相手に「申し訳ない」と思わせる。
14. フット・イン・ザ・ドア:
- 最初に小さな要求を受け入れさせ、徐々に大きな要求を通すテクニック。
- 例えば、アンケートに答えてもらうことから始め、最終的に商品を購入してもらう。
- 営業や、マーケティングで利用される。
- 段階的に要求をエスカレートさせることで、相手の警戒心を解く。
15. ミラーリング効果:
- 相手の言葉や動作を真似ることで親近感を抱かせるテクニック。
- 例えば、相手が腕を組んだら、自分も腕を組む。
- コミュニケーションを円滑にするために利用される。
- 相手に「自分と似ている」と思わせることで、安心感を与える。
16. バックトラッキング:
- 相手の言葉を繰り返すことで共感を示すテクニック。
- 例えば、相手が「今日は疲れた」と言ったら、「お疲れ様です」と返す。
- 傾聴の姿勢を示すために利用される。
- 相手の話をしっかりと聞いていることを伝える。
17. ペーシング:
- 相手のペースに合わせて話すことで信頼感を得るテクニック。
- 例えば、相手がゆっくり話す人なら、自分もゆっくり話す。
- コミュニケーションを円滑にするために利用される。
- 相手に合わせることで、安心感を与える。
18. フレーミング効果:
- 同じ内容でも表現方法によって印象が変わる現象。
- 例えば、「90%の確率で成功する」と言うのと、「10%の確率で失敗する」と言うのでは、印象が異なる。
- プレゼンテーションや、交渉で利用される。
- 伝えたい内容を、より効果的に表現する。
19. プロスペクト理論:
- 利益よりも損失を大きく感じてしまう心理傾向。
- 例えば、1000円もらうよりも、1000円失う方が、心理的なダメージが大きい。
- 投資や、ギャンブルなどで影響を受ける。
- 人は、利益よりも損失を回避しようとする傾向がある。
20. 損失回避の法則:
- 損をすることを極端に嫌う心理。
- 例えば、株で含み損が出ていると、損切りできずに持ち続けてしまう。
- プロスペクト理論とも関連する。
- 損失を確定することを避けようとする心理。
21〜30
21. 現状維持バイアス:
- 現状を変えたくない心理。
- 例えば、新しい仕事に挑戦するよりも、今の仕事を続ける方が安心する。
- 変化を恐れる心理から生まれる。
- 新しいことに挑戦することをためらう原因となる。
22. 認知バイアス:
- 思考の偏りによって、誤った判断をしてしまうこと。
- 例えば、確証バイアスや、アンカリング効果も認知バイアスの一種。
- 様々な種類があり、日常生活に影響を与える。
- 認知バイアスを理解することで、より客観的な判断ができるようになる。
23. 正常性バイアス:
- 危険な状況でも「自分は大丈夫」と思ってしまう心理。
- 例えば、災害が起こっても、「自分は大丈夫だろう」と思って避難しない。
- 防災意識を低下させる原因となる。
- 危機管理において、注意すべき心理現象。
24. 群集心理:
- 周りの人に流されてしまう心理。
- 例えば、デモや暴動に巻き込まれて、自分も同じ行動をしてしまう。
- 匿名性が高まると、群集心理が働きやすくなる。
- 集団行動の際に、注意が必要な心理現象。
25. 傍観者効果:
- 困っている人がいても、周りの人が多ければ助けない心理。
- 例えば、事件や事故現場で、周りの人が誰も助けないので、自分も助けない。
- 人数が多いほど、責任感が分散されるために起こる。
- 勇気を持って行動することが大切。
26. 社会的証明:
- 周りの人がしていることを正しいと思ってしまう心理。
- 例えば、人気のあるレストランに行列ができていると、自分も並んでしまう。
- バンドワゴン効果とも関連する。
- 人は、周りの人の行動を参考にすることが多い。
27.権威への服従:
- 権威のある人に従ってしまう心理。
- 例えば、医者や先生の言うことを信じてしまう。
- ミルグラム実験で示された。
- 権威のある人は、周りの人に影響を与えやすい。
28. アンダーマイニング効果:
- 報酬を与えることでモチベーションが下がる現象。
- 例えば、好きなことをしていたのに、報酬をもらうようになると、やる気がなくなる。
- 内発的動機づけが阻害されるために起こる。
- 報酬は、必ずしもモチベーションを高めるものではない。
29. ピグマリオン効果:
- 期待をかけることで相手の能力が伸びる現象。
- 例えば、教師が生徒に期待すると、生徒の成績が向上する。
- 教育現場で活用される。
- 期待は、相手の成長を促す力となる。
30. 自己成就予言:
- 自分の予想が現実になる現象。
- 例えば、「自分は成功する」と思っていると、本当に成功しやすくなる。
- ポジティブ思考が重要。
- 信念は、行動に影響を与え、結果として予言を現実化させる。
31〜40
31. 心理的リアクタンス:
- 自由を制限されると、反発したくなる心理。
- 例えば、「〇〇するな」と言われると、逆に〇〇したくなる。
- カリギュラ効果とも関連する。
- 人は、自由を求める欲求を持っている。
32. 認知再評価:
- ストレスを感じる出来事に対する考え方を変えることで、感情をコントロールするテクニック。
- 例えば、プレゼンテーション前に緊張しているときに、「これは成長の機会だ」と考える。
- ストレスマネジメントに有効。
- 出来事に対する解釈を変えることで、感情をコントロールすることができる。
33. 情動感染:
- 周りの人の感情に影響される現象。
- 例えば、悲しい映画を見ると、自分も悲しくなる。
- 共感性とも関連する。
- 人は、他者の感情に共鳴する能力を持っている。
34. 感情労働:
- 自分の感情を抑えて、相手に合わせた対応をする仕事。
- 例えば、接客業や介護職など。
- ストレスが溜まりやすい。
- 感情労働者は、心のケアが重要。
35. バーンアウト:
- 長期的なストレスによって、心身ともに疲弊した状態。
- 例えば、仕事のストレスが原因で、心身ともに疲れ果ててしまう。
- 休養やストレスマネジメントが必要。
- バーンアウトは、誰にでも起こりうる。
36. ストレス脆弱性モデル:
- ストレスに対する脆弱性(弱さ)と、ストレス要因の強さによって、ストレス反応が決まるというモデル。
- ストレスに弱い人でも、ストレス要因が弱ければ、ストレス反応は起こりにくい。
- ストレスマネジメントにおいて、重要な考え方。
- ストレス反応は、個人差が大きい。
37. コーピング:
- ストレスに対処するための行動や考え方。
- 問題焦点型コーピングと、情動焦点型コーピングがある。
- ストレスマネジメントにおいて、重要な概念。
- 自分に合ったコーピング方法を見つけることが大切。
38. 傾聴:
- 相手の話を注意深く聞くこと。
- コミュニケーションの基本。
- 相手に安心感を与える。
- 傾聴は、人間関係を良好にするために不可欠。
39. 共感:
- 相手の気持ちに寄り添うこと。
- 相手の気持ちを理解しようとすること。
- 傾聴と合わせて、良好な人間関係を築くために重要。
- 共感は、相手との信頼関係を深める。
40. アサーション:
- 自分の意見や気持ちを、相手に率直に伝えること。
- ただし、相手の気持ちも尊重する。
- アサーションスキルを身につけることで、より良いコミュニケーションが可能になる。
- アサーションは、自己肯定感を高める。
まとめ、心理学用語からこころのゆらぎをとらえて穏やかに暮らそう
心理学用語40選の話
でした。
人生100年で、
かなーり長い期間ぼくは
この心で暮らすことになっています。
なので少しでも心について
詳しくなりたくて
社会人になったいまも
片手間程度ですが、心理学の勉強してます。
またなにか思いついたら
ブログに書くことにしますね。
またなにか気づいたりメモしたくなる
心理学の用語があったら
しれっと追記します。